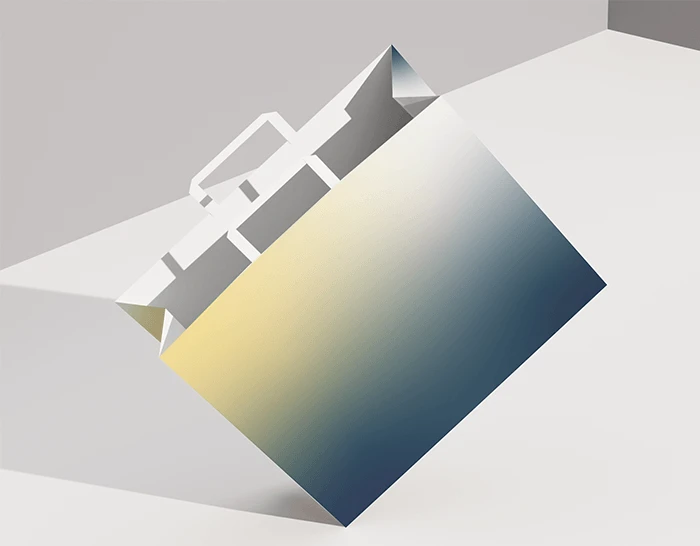マルイはデパート?異色の歴史とその経営
駅近接の商業施設として有名な「マルイ」。 かつての月賦百貨店の今と昔。

マルイは百貨店ではない
一般にマルイは百貨店(デパート)ではなくショッピングセンターとみなされる。
店舗が百貨店のような直営売り場よりも賃貸によるテナントを中心とした売り場構成であること。また日本百貨店協会へ未加盟であることから百貨店とは認識されていない。 しかし、そのルーツを探ると百貨店やファッションビルとは一線を画す異色の歴史が見えてくる。
月賦百貨店「丸井」
赤いカードの丸井は駅近で百貨店化を進めた
月賦百貨店とは割賦販売(分割払い)を前提とした販売を行う商業施設のこと。百貨店とは業態が異なり区別される。
クレジットカードが一般的ではない当時、家具や家電などの高額品を分割払いで購入することができる月賦百貨店は庶民の支持を集めた。月賦百貨店は丸井、緑屋(現セゾンカード)、丸興(現セディナ)が有力店であったが、1960年代後半から丸井は駅近の都心に大型店舗を展開する戦略をとり、月賦百貨店において業界首位とる。 その後、1970年代には百貨店が割賦販売に対応し、スーパーなどでもクレジットカードの利用が広まってゆく。
そこで丸井は「赤いカード」を発行して、自店以外での訴求を強化。時代に合わせてDCブランドをはじめとしたファッションカテゴリの強化や一括払いによる販売を始める。

ファッションビルのマルイ、
カード会社のマルイへ
時代に合わせて業態を変化させるマルイ
若者向けのアパレルを強化した丸井は1980年代から90年代の旺盛な消費に支えられ業容を拡大していく。 2000年代には売り場の4割が自主編集、6割が消化仕入れであり、現金販売も行ったことで百貨店と相違ない業態となっていた。
しかし2000年代後半から改正貸金業法によりクレジット販売やキャッシングにおける利息返還を迫られる。専門店やショッピングモール、製造小売業が台頭し、百貨店市場が縮小していくなかで百貨店に近いマルイもそのあおりを受けた。 2010年代初頭には最終赤字を計上、百貨店様の業態に陰りが見えるなか、2014年に町田マルイをリニューアル。このとき売り場をテナントに賃貸し、賃料収入を得る定借化を行った。
これを皮切りにマルイは全店で定借化を進め、従来の直営売り場を急速に減らしていく。ショッピングセンター業態に転換したマルイは2025年現在、定借化率は8割を超える。 同時にクレジットカード事業を強化、小売業としての店舗網を活かして「エポスカード」を広く展開。売上における金融事業の割合は7割に迫り、利益の多くを金融事業が稼ぐ構造となっている。

マルイの行く先
ショッピングセンター化、カード会社化したマルイはどこへ行くのか。
近年の特徴的な取り組みとして小売業、金融業と合わせてエンターテイメント業への積極投資が見られる。 アニメやキャラクターなどのサブカルチャーに焦点を当てイベントによる集客を通して「好き」に支えられるファン消費の取り込みを図っている。
一方で急速に進めた定借化は館のコモディティ化を招くほか、需要を利益に転嫁しにくくなるデメリットも抱える。金融事業の存在感が強くなるなか、小売業として販売力や集客力をどう保つかは注目すべき動きだ。百貨店とは異なる道を進み、時代に合わせてその業態を変化させることで生き残ってきたマルイから学ぶことは多い。

※正確には「株式会社丸井」による店舗ブランド「マルイ」。ただし本稿では構成と背景を明確にするため、月賦百貨店の業態を丸井、現在の業態をマルイとして表記した。
最新記事
もっと知る百貨店
日本百貨店協会
一般社団法人日本百貨店協会。全国の各百貨店でつくる業界団体、すべての百貨店が加盟している。加盟している百貨店と系列企業では全国百貨店共通商品券が利用できる。
自主編集売り場
百貨店が直営で自ら商品を編集して販売する売り場。テーマを持った商品展開であったり、複数のカテゴリを組み合わせた商品展開など特徴を持たせて販売する。例えば特定のデザイナーを集めた販売や、スーツやバッグ、ネクタイまで組み合わせてスタイルを提案する販売などがある。90年代に伊勢丹が展開した「解放区」が有名。従来の消化仕入れとは異なり、買取仕入れで百貨店が在庫リスクを負う。
消化仕入れ
百貨店の大部分を占める仕入れ方式。売り場に並ぶ商品はアパレルなどのメーカーのもの→レジを通した際に百貨店のものとなり→直後お客様に渡される。この方式により百貨店は在庫リスクを抱えず、メーカー側は柔軟に商品の移動ができる。一方で接客や編集をメーカーに任せた商習慣は百貨店の競争力を低下させているという指摘もある。
製造小売業
商品の製造から販売までを一貫して行う企業。SPAとも。ニトリやユニクロ、JINSなどがあたる。低価格で統一したイメージによる大量の商品展開は、多品種総合販売が特徴の百貨店にとって強い競合となった。