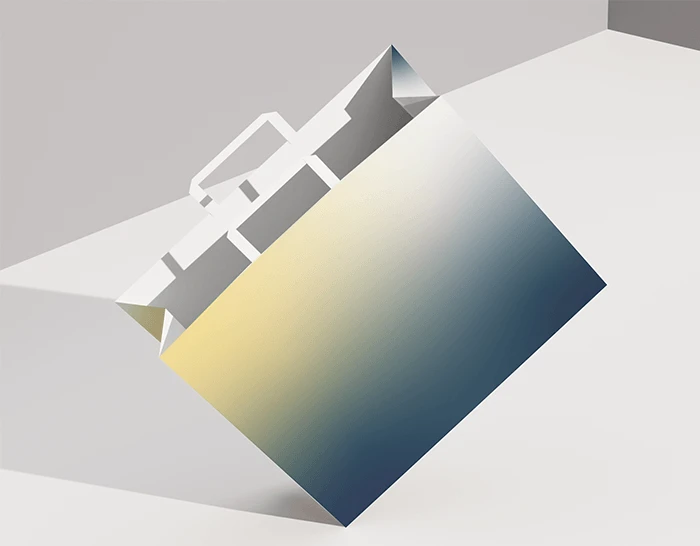地下鉄とつながる百貨店
1920年代、大阪で百貨店と駅が直結。ターミナルデパートが誕生するなか、東京では国内初の地下鉄である銀座線が開業して百貨店と地下鉄駅が直結した。後に地下鉄は百貨店にとって重要な接点になってゆく。【シリーズ:駅と百貨店】

上野広小路駅
日本で初めて百貨店と直結した地下鉄駅
上野広小路駅は銀座線で渋谷方面に向かうとき、上野駅の次にある駅。後述の三越前駅が著名であるため、あまり知名度は高くないがこの駅は同地で営業する百貨店「松坂屋」が建設資金の一部を負担して設けた駅だ。

1930年に開業した上野広小路駅は当初設置される計画はなかった。地下鉄建設をみた当時松坂屋専務が同級生であった東京地下鉄道の社長に申し入れを行い、設置されることとなった駅である。そのため松坂屋が建設費の全額負担には至らず、三越前駅設置の計画のほうが早かったことから「松坂屋前駅」とすることができなかった。松坂屋が負担したのは床や天井などの装飾費と出入口の建設費。銀座線の延伸開業にあわせて松坂屋の地下階と駅が直結することとなり日本で初めて百貨店と地下鉄が直結した。

三越前駅
駅の建設費を全額負担。三越の名を冠した豪華な地下鉄駅。
上野広小路駅の開業から2年後、銀座線は神田駅から三越駅まで延伸した。三越前駅はその名の通り三越日本橋本店に直結した地下鉄駅であり、三越が建設費のほぼ全額を負担して設置された。計画は銀座線の初期からあり、浅草ー上野間の地下鉄建設工事をみた三井銀行の池田成彬が三越前駅の設置を提案したと伝えられている。周到に準備された建設では日本初のエスカレーターの設置、大型のショーウィンドウ、大理石でしつらえた連絡通路が設けられた。連絡通路には当時流行したアール・デコ様式の装飾がフランスの装飾家ルネ・プルーによって手掛けられ、現代からみても豪華な造りの地下鉄駅であった。



銀座線と百貨店のその後
日本橋から銀座まで。百貨店が地下鉄建設を支えた。
上に挙げた2つの駅以外にも銀座線は多くの百貨店から支援を受けて建設され、現在も百貨店と直結している。日本橋駅は高島屋と当時の白木屋(後の東急百貨店日本橋店、現在はコレド日本橋)が折半して設置された駅であり、京橋駅の建設にはスーパーの明治屋が、銀座駅の建設には銀座三越と松屋銀座が関わっている。地下鉄と百貨店の直結に三越の役割は大きいが、そもそも地下鉄自体が百貨店をはじめとした都心を通るように計画されたこともあり、直結は必然的な流れであった。百貨店に支えられた都心部の地下鉄建設は現代において欠かせない交通インフラとなっている。百貨店も地下鉄という新たな接点を得たことで集客力を強化しただけでなく、後の時代においてデパ地下の拡大など百貨店の戦略にも影響を与えた。